(前に戻る場合はこちらへ)
(前に戻る場合はこちらへ)
右は、スピーカーのインピーダンス特性と類似のインピーダンス特性が生じるように組んだ回路。言い換えれば、インピーダンス特性にかかるスピーカーの等価回路。
これを使用して電流出力アンプにスピーカーを繋いだ場合、どのような出力電圧/周波数特性が得られるのかシミュレーションしてみる。
使用するのは評価版PSpice。
まったく間の抜けた話しだが、こういう便利なものが安く手に入るものとは認識していなかった。非常に高機能らしいので、私のレベルでは評価版で十分(^^;だが・・・
今回は、オペアンプと幾つかのLCRを使って理念型的なシミュレーションとなる。
ここに使用するOPアンプは、オープンゲイン120dbで周波数特性がフラット、入力インピーダンス∞、出力インピーダンス0Ωという、ほぼ理想的OPアンプ。LCRも理想的LCR。
だから、現実のDCアンプを使用した場合とはちょっと条件が違う筈なので、現実にもこういう結果が得られるというものではないが、傾向は良く分かる。
まあ、シミュレーションとはそういうものか。あくまで道具だから使いよう、ということだ。
なにせ、ブラックボックスだから、正しい結果なのかどうかは不明だし・・・(^^;
まずは、この等価回路がどのようなインピーダンス特性を持っているのか、本当に現実のスピーカーのインピーダンス特性に類似の特性となっているのか、を確かめるために、電流出力アンプでドライブして出力電圧特性を観察する。
そこでこの回路。電流負帰還による電流出力アンプである。
この場合、出力電圧ゲインはb/aだから、a=1Ω、入力電圧1Vacなので、OPアンプの出力電圧(V)がそのまま負荷のインピーダンス(Ω)を表すことになる。
回路を作り上げてブローブを取り付けRUNすると・・・、附属のオッシロ(おっと、そうじゃなかった。FFTか?)が即座に結果を表示してくれる。う〜ん、なんとも便利だ(^^)
こんなものがタダで雑誌の付録に付いてくるとは・・・良い世の中になったものだ。 MJもたまにDCマイク使用(とまでの贅沢はいわないが)生録CDでも付録に付けてくれればもっと売れるだろうに・・・
結果、最低インピーダンスは8Ω。低域の共振周波数は55Hz付近でそこでのインピーダンスは53Ω。さらに1kHz付近からインピーダンスが上昇し、20kHz付近では22Ω程度で、まあ、それなりにスピーカのインピーダンス特性をシミュレートしているものであることが分かる。
逆に言うと、電流負帰還による電流出力アンプの出力電圧特性は、スピーカーのインピーダンス特性相似の特性になるということである訳だ。スピーカーのfoでは、この場合スピーカーのインピーダンスが53Ωと8Ωの6.63倍だから、出力電圧も6.63倍、出力電力としては43倍もの出力になる(もとい。訂正。インピーダンスも6.63倍だから出力電力もやはり6.63倍でした。)ことになる。高域のインピーダンスが盛り上がる領域も同様だ。電流出力アンプを作る場合は、特にfo付近での出力電圧の急激な盛り上がりでアンプ自体が飽和してしまわないように留意しなければならないだろう。
その結果、fo付近の音がこのように急激に盛り上がったものになるかどうかは分からないが(多分そうはならないのだろう)、少なくとも高域の音圧は上がるものと思われるので、それで聞こえなかった高音が聞こえるようになって音が良くなったように思えたり、逆に高音の荒れた感じが出て音が悪くなったと感じたり、なんてことはありえそうだ。
次に、これを電圧負帰還による電圧出力のOPアンプでドライブしてみる。
世の中のアンプは大体これで、K式MFBを用いない金田式DCアンプもこの状態だ。
結果はご覧のとおりで、アンプの出力電圧はスピーカーのインピーダンス特性とは全く関係なくフラットとなっている。
現代スピーカーは、このようなフラットな周波数特性(電圧駆動)のアンプでドライブされたときにフラットな周波数特性が得られるように作られている、というのがいわゆる通説。
では、金田式MFBではどのような特性が得られるのか、のシミュレーションをしてみたのがこれ。
“MFB”については、また別の視点での議論なのでそれは置いておくとして、単純に言えばあの帰還回路構成は、電圧負帰還と電流負帰還を併用して金田式DCアンプを適度な正の出力インピーダンスを有する電流出力アンプとするためのものであることが分かる。
これはCNFマックスの場合をシミュレートしたものだが、得られる電圧ゲイン周波数特性は電流出力アンプのものそのものだ。
ついでに特性図からこのアンプの出力インピーダンスは5.7Ω程度と計算されるが、現実の金田式DCアンプではこの帰還回路定数でそれほど大きな正の出力インピーダンスにはならない。やはり、オープンループゲインが1000倍も違うことの影響かもしれない。
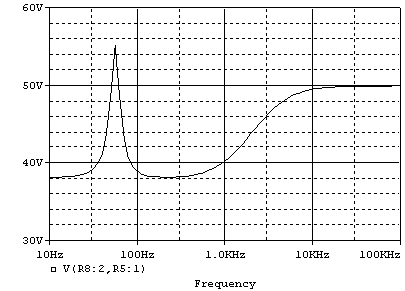
これも同じく金田式MFBのシミュレーション。ただし、こちらはVNFマックスの場合。
これでも電流出力アンプ状態ではあるが、インピーダンス特性相似の盛り上がりは大分小さくなっており、かなり電圧出力アンプに近づいている。
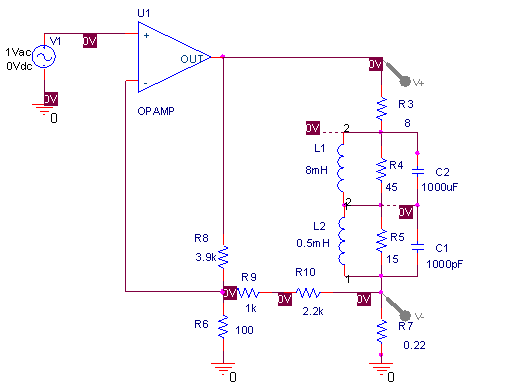
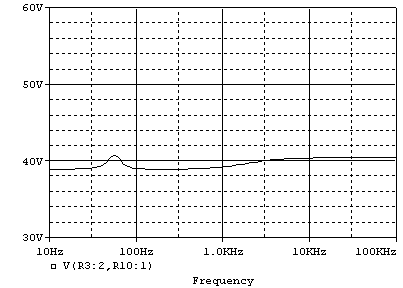
そして、これが今回の反転型電流正帰還アンプのシミュレーション。
ここでは特性変化が顕著に現れるように電流検出抵抗を0.47Ωにしてある。また、パラメトリック解析というものを活用し、R8を0Ωから200Ωずつ1kΩまで変化させた場合の結果を1回のRUNで得ている。要するに右図で、一番上がR8=0Ωの電流正帰還最大の時の出力電圧特性で、順に200Ω、400Ωの場合となって、一番下がR8=1kΩの電流正帰還最小の時の特性だ。要するに、R8を0Ωから1kΩまで変化させた場合の特性の変化が連続的にこのようになるということ。
予想された結果ではあるのだが、なかなかに興味深い。
まず、電流負帰還で正の出力インピーダンスとなっているいわゆる電流出力アンプの場合とは対称的に、負荷のインピーダンスが増加すると逆に電圧ゲインが減少しており、結果特性図がインピーダンス特性を180°反転させたようなものになっていることだ。
負性インピーダンスの面目躍如といった感じだが、特性図から計算すると、出力インピーダンスは最大で−5.3Ω程度である。
今ひとつ。この特性がインピーダンス特性を180°反転させたようなものとは言っても、インピーダンス特性や正のインピーダンスを持つ電流出力アンプの特性と線対称であるわけではないこと。要するに、スピーカーのインピーダンスが上昇する部分で電圧ゲインが減少すると言うより、スピーカーのインピーダンスが小さい部分で電圧ゲインが上昇する、といった方が適切な特性になっているということだ。
それに、スピーカのfoでのインピーダンス上昇がもたらすピークの鋭さが大分ブロードになっている点も、出力インピーダンスが正の電流出力アンプとは異なる点だ。
・・・・・・
普通、こういう出力電圧特性を見たら、このアンプをまともな音がするアンプとして認める人はいないのではないだろうか。重低音領域と中域に著しい盛り上がりを持つとんでもないアンプとしか思えないですなぁ。やはり、負性インピーダンスアンプなどというものは作ってはいけないですね(^^;
これも同じく今回の反転型電流正帰還アンプのシミュレーション。
電流検出抵抗を0.22Ωとしたので、上の場合ほど顕著に特異な特性図とはなっていないので、大したものではないようにも見える。のだが、縦軸がリニアなので直感的に分かりにくいだけで、実は電圧ゲイン差を計算すると、これで上の金田式MFBのCNFマックスの場合と同程度の電圧ゲイン差が得られていることが分かる。
ま、やはり、この辺が上手い塩梅なのではなかろうか。(^^)
最後に、Λ式MFB。非反転型電流正帰還アンプの場合のシミュレーション。
ここでもパラメトリック解析を活用し、R6を51kΩから1kΩまで5kΩ毎に減少させて電流正帰還量を増加させていった場合の出力電圧特性を得ている。
右の特性図の一番上がR6=51kΩの場合の特性で、以下46kΩ、41kΩ、・・・、一番下がR6=1kΩの場合の特性だ。
この場合も反転型と同じく負性出力インピーダンスのアンプが有する出力電圧特性になることが分かる。
R6を減少させて電流正帰還量を増やすほどに負性インピーダンス特性が顕著になり、結局負の出力インピーダンスの絶対値が大きくなることがわかるが、併せて電圧ゲイン自体も小さくなってしまう。という点が、この方式の欠点といえば欠点だろう。
が、アンプに対する簡単な知識さえあれば、Λ式MFBアダプタを作ってアンプに簡単に付加して試すことが出来て、いつでも又元に戻せるというのは大きなメリットだ。
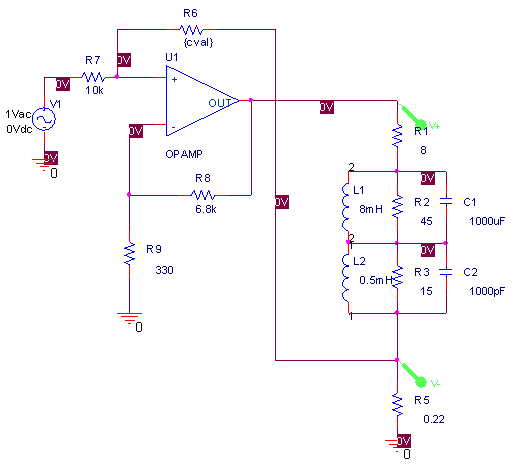
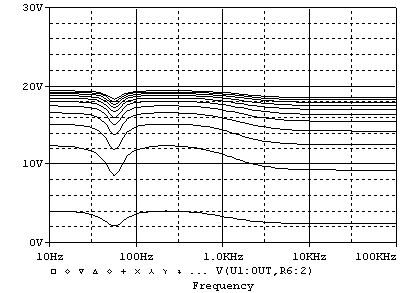
(2002.5.18)